「それは違うんじゃない?」相手が間違った情報を信じているとき、つい口に出したくなる言葉です。しかし、その一言がきっかけで空気がピリッと張りつめ、相手が感情的に反論してきた・・・そんな経験はありませんか?
本当は正しい情報を共有したいという思いから出た言葉なのに、いつの間にか「どちらが正しいか」という勝負のようになってしまう。こうした意見の衝突は、職場、家庭、友人、SNS上でも誰しも起こり得るものです。
なぜ人は自分の考えに固執し、対立が生まれてしまうのでしょうか。そこには「認知の歪み」と呼ばれる思考のクセが深く関わっています。
なぜ意見が衝突するのか?〜認知の歪みの存在
私たちは日々の出来事を「ありのまま」に受け取っているようで、実際には自分なりの解釈を通して理解しています。ここで影響を与えているのが「認知の歪み」です。
例えば、相手が信じている情報に対して、
・「私は間違っていないはずだ」と思い込む→認証バイアス
・「相手が間違い、自分は正しい」→白黒思考(二分法)
このように思考が極端になると、互いに譲らない状態が生まれやすくなります。認知の歪みは誰にでもあるものですが、それが強く働くと小さな違いが大きな衝突に発展してしまうのです。
衝突を和らげる3つのステップ
では、どうすれば衝突を避けつつ、相手に正しい情報を伝えられるのでしょうか。
ここでは「認知の歪みを柔らかく修正する」ための3つのステップをご紹介します。
①いったん受け止める
相手が何かを信じているとき、すぐに「それは違う」と指摘すると、された相手は防衛反応が働きます。まずは「そう思ったんだね」と受け止めてあげましょう。受容の姿勢は、相手の心を開きやすくします。
②視点を広げる
次に「別の見方もあるかも知れない」と柔らかく提案をします。ここで重要なのは、「正しい/間違い」という二分法を避けること。複数の可能性を提示することで、相手も「自分の考えを否定された」と感じにくくなります。
③情報を共有する
最後に「実はこういう資料を見たよ」と、事実を”共有”する形で伝えます。対立ではなく「一緒に情報を確認する」スタンスを取ると、相手も受け入れやすくなります。
正しさよりも大切なこと
意見が対立する場面では、「相手を正すこと」よりも「関係を保つこと」が大切です。正しさを押し付けても、相手が納得しなければ意味がありません。むしろ「正しさを証明しようとすればするほど関係が悪化する」ということも多いのです。
認知の歪みを修正するときは、相手を説得することではなく、お互いの受け取り方のクセをやわらげることが大切です。その結果として、対立が解消されたり、建設的な対話につながったりします。
まとめ
・意見の衝突の背景には「認知の歪み(思考のクセ)」がある
・対立をやわらげるには、①受け止める、②視点を広げる、③情報を共有する、の3ステップが有効。
・大切なのは「正しさ」よりも「対話と関係性」
誰にでも起こり得る意見の衝突。そこに心理学の視点を取り入れるだけで、対立を避け、よりよい人間関係を築くことができます。
完璧でなくても大丈夫です。最初の一歩は「相手を否定しないで聞いてみる」だけで十分です。
あなたの人間関係が穏やかで温かいものになりますように。
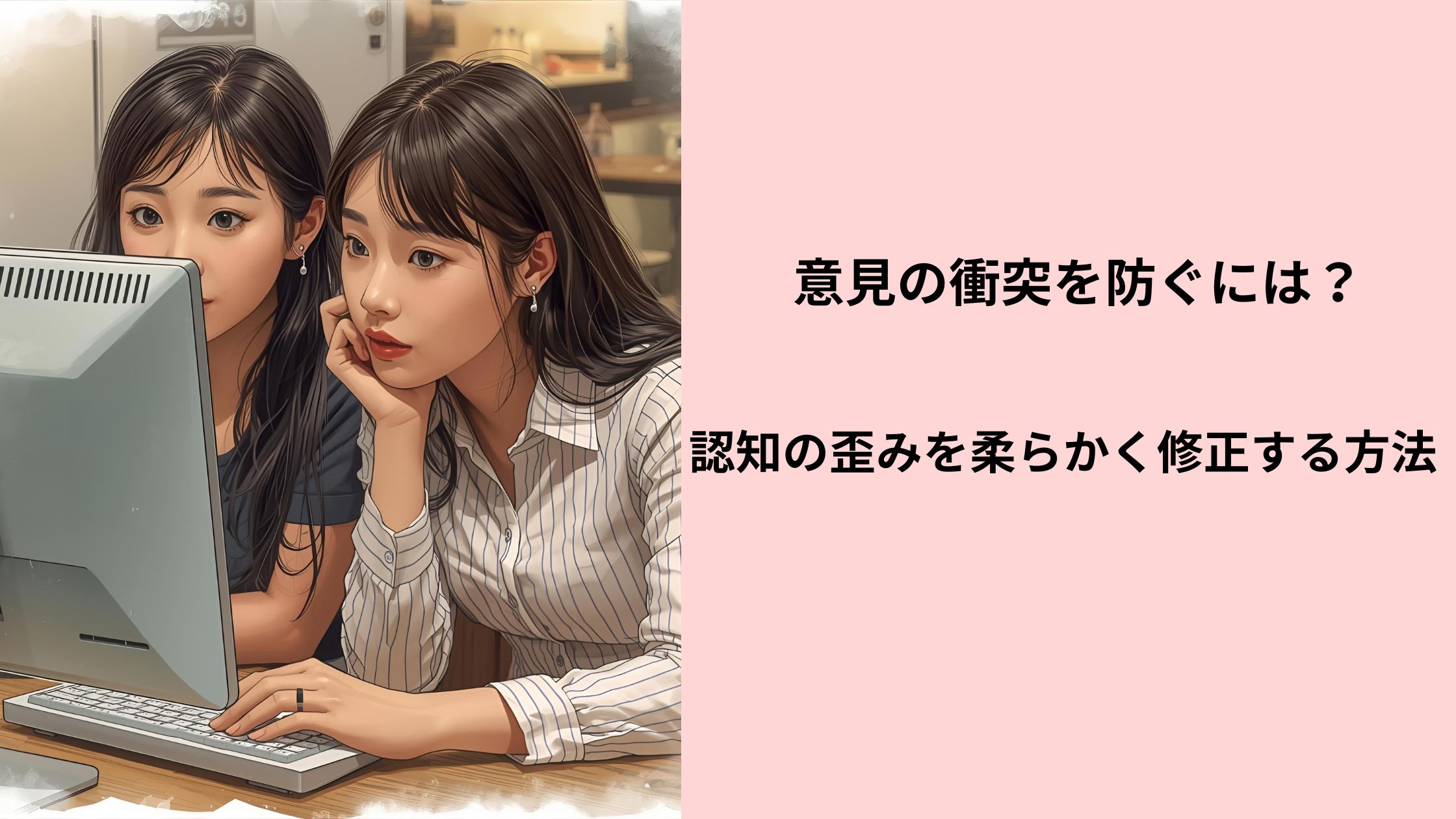
コメント